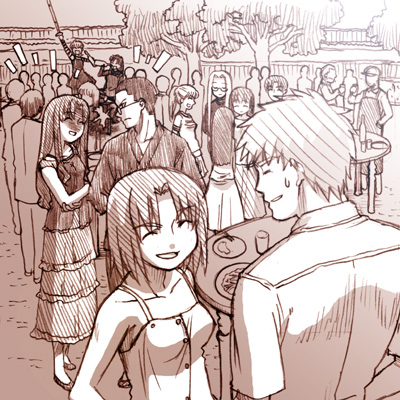
過ぎた日々は今も
夕日が沈み始めるころ。
なんと名づけていいのかわからない飲み会は開催された。
「ととと……」
炒め物を載せた皿を3枚同時に運ぶ士郎。
「酒もってこーーい!」
「わははははは」
もうすでに出来上がり始めている藤ねぇが奥のテーブルで
ネコさんと一緒に騒いでいる。
その周りにいる人は穂群原の関係者だったり御近所の方だったりと
じつに多様である。
「おーい、藤ねぇ、明日が本番なんだからあんまり飲むなよ〜」
「大丈夫大丈夫〜」
あまり大丈夫ではなさそうだが。
「やあ士郎くん」
苦笑しながら歩く士郎に
コペンハーゲンのおやじさんが声をかけてくる。
「まだ早いけど今回はおめでとう」
「あ、ありがとうございます。
はー、馬鹿虎のせいでなんかいろいろ
お世話になっちゃって………すいません」
「あっはっは、気にすることないよ。
士郎くんがうちでバイトしてくれていたころは本当に助かっていたし。
………何年になるかな……。
8年かな?結局」
「そうですね………。
学校出た後もバイトさせてもらってましたから」
「あはは、それだけ一緒にいればもう息子も同然だよ」
そういって士郎の肩を叩くおやじさん。
「………本当に、ありがとうございました」
笑うおやじさんに深く頭を下げる士郎。それをみておやじさんは
目を細める。
「本当によかったねぇ。……大事にしてやるんだよ?」
「はい………」
もう一度だけ深く頭を下げて士郎はその場を辞す。
そうして、愛する人を目で探す。
桜は弓道部の面々と楽しげに話していた。
そうして話している様は、一緒に過ごした学園での最後の一年を
士郎に思い出させる。
桜は変わった。
学園ではおとなしかった桜。
後で聞いた話だが、士郎が聖杯戦争後
行方不明になっていたときの学校での桜は
とてもとても……明るかったらしい。
―――痛々しいほどに。
居なくなってしまった人の気配を
自分が明るくなることで埋めるかのように。
いつ士郎がこの場所へ戻ってきても大丈夫なように。
そうして、よく体調を悪くしていた。
人間、そう簡単に変われるものではない。
ましてや、桜のそれは明らかな無理だった。
立っていられないほどの状況で飛び回っているようなものだ。
そのころの桜の事を聞くと藤ねぇですら、言葉を濁す。
……そうして士郎が帰ってきて、一緒に学校に行くようになって、
罪の意識と前向きに向き合えるようになって。
―――最後の一年。
桜は、作ってきた学園での自分を現実にしようとするかのように、
がんばってがんばって、士郎と共に明るく楽しく過ごした。
元々美しい桜だ。弓道部の部長になってたくさんの新入生が
はいってくると、彼らにとても慕われるようになった。
その頃から桜は体調を崩さなくなった。
桜の笑顔は本物になったのだ。
そうして、その姿は今の桜へと繋がる。
自分の事を思ってくれる人たちと話すその姿は、本当に輝いていて。
「………………ふ」
よかったな、と士郎は思う。
「なーにニヤニヤしてんのよ」
いつのまにか、後ろにいた凛と美綴はそんな士郎の姿を見て
にやにやと笑っていた。
「―――ん。なんでもない」
手に持った炒め物をテーブルにおいて二人に向き直る士郎。
「衛宮、結婚おめでとうな」
にかっと笑って祝辞を言ってきたのは美綴綾子である。
「ああ、ありがとう。美綴にはすげー感謝してるよ。
桜の事とか、学校出た後もいろいろ力になってくれたからな」
「気にするな。ま、あんたがあんまりにも唐変木なんで
みてられなかったというのもあるんだけどな」
「―――む」
黙り込む士郎。
在学中、社会人になってからも
美綴は二人の為に良く力になってくれて、実質
士郎と桜の共通の友人であった。
「あはは、でもなんだかんだ結婚する甲斐性はあって
ほっとしてるよ、あたしは」
「ぷぷ……いくらなんでも言い過ぎだって、綾子」
「―――むぅ。そんなに甲斐性無しに見えるか?俺」
「見える見える。明日結婚式だってのに桜とケンカ中だって?」
「―――遠坂」
「違う違う、私じゃない」
「くくく……藤村先生だよ」
「あ………の馬鹿虎ーーー!」
真っ赤になって藤ねぇを睨みつける士郎。何を勘違いしたのか
藤ねぇはそんな士郎に手を振り返してくる。
「あのへんに集まってる人には筒抜けかもね……」
「くそぉ………」
一人になりたい気分だった。
「衛宮ー、楽しくやっておるか………む……遠坂……」
項垂れた士郎に声をかけてきたのは一成だった。
「何をしている。
めでたい日にそのような魔性のものと一緒にいては
悪運に取り付かれるぞ」
ピキーン。
……一同の間に冷たい空気が走る。
冷や汗をかきながら凛の方を見ると案の定―――
とてもとても怖い顔をしていた。
張り付いたような笑顔。この顔の遠坂凛は、怖い。
「……だれが魔性のものですって?柳洞くん?」
「黄泉の者が人をたぶらかす時に自分は悪鬼の類です、とでも
いうと思うのか?たわけ」
表面上冷静に見える二人だが
そのオーラはまさにかみつかんとせんばかり。
「うわー……俺がいない一年でこの二人何があったんだ?
一成も第一声でこんなこと言う奴じゃなかったと思うんだけど……」
「んー。まああんたがいない間の事、自分より遠坂が知っていたのが
ずいぶんと気に食わなかったみたいでねー。
ま、それから暗闘悲喜交々。なむー、ってね」
合掌。
「ま、口とか態度とかはあんな感じだけど、一成のほうも
内心そこまで遠坂のこと嫌ってないと思うけどね」
「………そうか?
どう見ても地獄に落ちろというような内容の
会話をしているように思えるんだけど……」
「なんだかんだ、遠坂が衛宮の事考えていろいろやってたのは
気がついてるみたいだし、アンタが一緒に卒業できるように
一緒になって働きかけてたのもあの二人だしね。
………ま、その願いも叶わなかったけどさ」
「………そっか」
「ま………あの二人流の親愛表現とかいうやつ?」
そういって笑いあう二人。
「……な、遠坂、一成」
「……なによ?」「……なんだ?」
冷戦止まりそうに無い二人に話しかける士郎。
「良かったら向こうのほうで話さないか?
折角久々に顔あわせたんだ。
ケンカばっかってのもどうかと思うしさ」
「………む、確かに大人気なかった。
修行が足りんな……精進せねば、喝。
―――すまぬ遠坂」
「―――ふん。
ま、出された矛引かれたならやる意味はないわ。
いいわ、じゃ少し歩きましょうか」
そういって矛先を収める二人。
それで険悪な雰囲気は微塵も残さず消え去った。
「……な?」
「だな」
士郎と美綴は顔を見合わせて笑う。
「なによ?」「なんだ?」
そうして四人は夜の帳が落ち始める衛宮邸の庭を歩き出した。
士郎の結婚前夜編その7。
過ぎた日々は過去になっても
共に過ごした日々の思いは消えない。