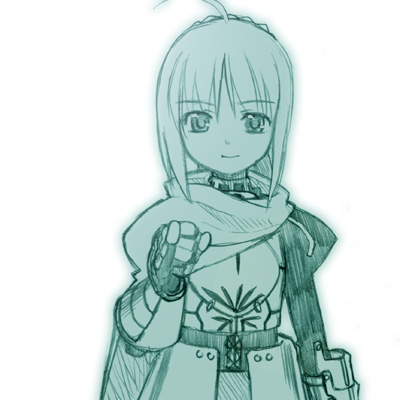
また、何処かで
竜はその巨体を黒い池から起こすと、
山肌に居る二人のサーヴァントを見つめ、眼窩に敵意を灯らせる。
「―――っ!」
体を硬直させようとする強烈な悪意を振り払い、二人は
同方向へと跳躍する。その瞬間、竜の顎から放たれる巨大な黒い魔弾。
ゴシャアアアアッ!!
山肌に命中し弾ける億の呪い。一瞬前まで二人が居た山肌は
竜の放った魔弾により汚染され、死の大地と化していた。
「
「………指向性を持たせた大質量の呪い………
ガンドなどというレベルではないな」
竜は緩慢な動作で振り向き、二人を追ってくる。
まだ覚醒したてで体の制御が利かないのか、今の彼の動きならば
こちらを捉えることは出来まい。
「ち………どうするか」
「本体を叩くしか無いでしょうね。
寄代を使い具現化しているということは、アンリマユは
“自身の体”を未だ持っていないという事になる。
ならば、彼が受肉する前に大聖杯を叩き、魔力の供給元を
断ってしまえば、これだけの大質量維持できなくなるでしょう」
「………………」
目を細め、眉を寄せてセイバーを見る。
それは、この状況では選びようも無い最良の策。彼女にはそれを可能とするだけの
武装がある。だが同時に―――それを行うという事は彼女の死を意味する。
「………なんて顔をしているのですか。
全く、貴方は………………」
「む、顔に出るとは………」
崖に切り立つ岩棚の後ろに滑り込むと、セイバーはアーチャーの顔を見つめ
苦笑を浮かべる。よほど酷い顔をしているのだろう。
彼女の眼差しは、まるで泣いている弟をみつめる姉のような慈しみがあった。
―――キュン―――ズバッ!!!
その時、アーチャー達が隠れていた岩棚が斜めに切り裂かれる。
慌てて身を翻すと岩棚から離れ黒い竜を見据える。
その体から見境無く放たれているのは泥で出来た糸………否。
超高圧で噴出されるウォーターカッターとも言うべきものだった。
「冬木の竜神の能力か………!
形を模すだけではなく能力まで再現するとはな」
空間を切り裂き走る強力な水の刃を潜りながら逃げ回る二人。
首を向けずに放てる水の刃は強力な武器だ。
しかも呪いの付加効果も付き、当たれば確実に致命傷となるだろう。
「アーチャー」
「―――ああ」
もう、自分のつまらない感傷で引き伸ばせる状況ではない。
目の前の竜を倒すには、セイバーの策以外に方法は無い。
山肌を駆け上り、体勢を立て直すために丘陵に隠れた二人は
荒い息をつき互いの顔を見つめる。
「………ふぅ。
アーチャー、一つ約束をしませんか」
「………約束?」
そう言ってにっこり笑うとセイバーは小指をアーチャーの前に向ける。
「………く。それはまず約束の内容を言ってからするものだぞ」
「む、そうでしたか。
では………。
何時かまた出会えたとき、貴方達の事を教えて欲しい」
「――――――」
それは………明らかに。
叶わぬ約束だった。
「それは………だが」
「………駄目ですか」
「そうあからさまにしょんぼりとされると困るのだが………」
「私は貴方達に興味がわいた。
此度の邂逅ではそれを聞く為の時間を得られませんでした。
ですから、また会えたとき。
今度は刃を交えることなく………貴方と語らいたいと思ったのです」
「――――――」
それはなんて………魅力的な願いなのだろうか。
刃を合わせることなく、ただ互いの事を語らう。
ああ、そんな風に笑って話せる日のことを、どれだけ夢見て過ごして来ただろう。
叶うものならば叶えたい。
「………断る理由は無い。だが、叶えられるか判らない約束だぞ」
「いいえ。約束を叶えようとする思いがあれば、
私達は何処かの未来できっと出会える」
「………未来?」
「そう、未来だ。貴方も私も既に死したる身。
だが、ここで出会えた僥倖があるように、
例え滅びても願う想いがあるのなら終わったわけでは無い。
約束は未来への灯火だ。その灯火を目指し、また走り出せばいいのです」
「―――――――――」
セイバーを見つめる。その顔に浮かぶのは死を迎える者の色ではない。
明日を望む人間の笑み。
未来を尊ぶ者の浮かべる笑顔だ。
………そうか。これは別れではないのだ。
いつか出会う日までの、ほんの挨拶―――。
「それとも、このような願いでは不服か? アーチャー」
「いいや………是非も無い。必ずや、騎士王」
そうして、王と騎士は指きりを交わす。
彼女の掲げる灯火はきっと黄金。どんな暗闇の中でも迷う事は無いだろう。
だからきっと―――また出会える。
「貴方の答え………この胸に刻んでおく」
「ああ、そうしてくれ」
「………思い出話を、楽しみにしておきましょう」
「………ああ」
「命は大切にするのですよ?」
「くく、君は母親か何かかね?」
「いいえ、共に戦った戦友だ」
「………承知した」
―――キュン―――ザザッ!!
二人が隠れる丘陵を狙い撃ちするかのように迫り来る刃。
丘を離れ、二人の英雄は黒い竜と対する。
「では―――往きます」
「ああ、後は任せておけ。存分に、騎士王」
「はい。
行くぞ―――“
攻撃を縫って山肌を疾駆しながら竜の頭を目指す。
こちらに向かって呪力弾を放つため竜の顎が向いた瞬間、
二人はそれぞれ逆方向へと跳ぶ。
アーチャーは竜の頭と逆側へと跳び、
セイバーは地を蹴り―――竜の頭へと飛び込む。
『湖の乙女よ―――契約の我が身を、彼の地へと導き給え………!』
翳した腕に灯る黄金の輝き。この戦いにおいて多くの命を守ってきた
黄金の鞘がセイバーの腕から宙へと姿を現す。
其は人の辿り着けぬ聖地。この世の果て、りんごの木が生い茂るという
星の魂が望んだ理想郷―――
「“
ギィン――――――!
鞘は主の求めに応じ、幾百の光の粒となり“理想郷”を具現化させる。
それは、主の身を護る究極の結界。ありとあらゆる意思の干渉を断ち、
全てを寄せ付けぬ最強の護り。
光に包まれたセイバーは放たれた呪力弾を物ともせず竜の体内へと突入する。
グオオオオオオオオオオオオオオオオオッ―――!!
体内に入り込んだ異物に苦しみ、竜が咆哮をあげる。
セイバーはここから竜の体内を通して、魔力の供給路を遡り
大聖杯まで向かう事になる。それを成すまで目前のデカブツを
引き止めておくのが自分の仕事だ。
「さて―――竜退治と参ろうか………!」
家政夫と一緒編第四部その36。
一つの別れは悲しい。道は二つに分かれ、何処までも伸びていく。
けれど進む足があるならば、いつかまた出会える。
だから挨拶を交わして違う道を往こう。
また、何処かで。