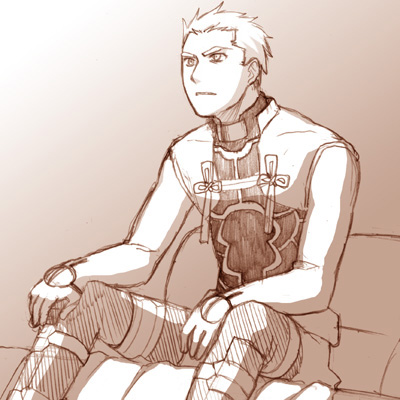
魔術師と守護者
「―――聖杯の、破壊………だと?」
遠坂邸応接室、22時過ぎ。
アーチャーと時臣、二人の長躯は
豪華な来賓用テーブルを挟んで向かい合っていた。
眠ってしまった子供達を寝室に運んだアーチャーは、
居間に残っていた時臣に聖杯戦争について相談があると切り出した。
半ば予感していたのだろう。
頷き一つ、時臣はアーチャーの提案に応じ今に至る。
―――アーチャーの目的は、聖杯戦争の恒久的終結。
術式の完全破壊である。
その為には“龍の腸”にあるという大聖杯の破壊を
成し遂げなければならない。
持ち主の願いを叶え、願望機として完成するといわれる冬木の聖杯だが、
表向きに“聖杯”と呼ばれる被造物はその実、
英霊の魂を保存し、空間に根源と繋がる穴を穿つための炉心に過ぎず、
奇跡じみた力など持たない。
云わば岩盤を打ち破るためのダイナマイトだ。
聖杯戦争を運営し、実行してきたのは、“大聖杯”と呼ばれる
巨大な魔術回路の方である。
聖杯戦争というシステムを破壊しようと思うのならば、
壊すべきは道具ではなく本体。術式そのものだ。
「ああ、その通りだ。
その為に龍の腸とやらの位置を貴方に伺いたい。
遠坂時臣」
「……………。
それは、遠坂の魔術師がこのシステムの管理人だと知って
頼んでいるのか、サーヴァント?」
「――――――無論」
二人の間に緊張が走る。
それは、主と従が互いの権益を破壊するぞと脅しあう構図。
「その頼みが、今現在冬木にいる魔術師にとって
どれほど受け入れがたい頼みなのか。
おまえにはわかっているはずだな?アーチャー」
「―――ああ、判っている」
「ならば、首を縦に振るわけが無いだろう。
真っ正直にそんなことを頼んでくるとは、
おまえはもう少し頭の回るサーヴァントだと思っていたのだがな、アーチャー」
険悪な表情でアーチャーを睨みつける時臣。
予想していたことではあるが、案の定こうなった。
アーチャーは苦虫を噛み潰したような表情で腕を組む。
さて、どう攻めるか。
「………なぜだ」
「―――む?」
「アーチャー、何故聖杯を破壊したいと願う?
おまえが聖杯自体に興味を持っていないのは、
昨日のセイバーとの会話で概ね理解できた。
だが何故―――破壊する必要があるのだ?」
少々険を和らげて時臣は尋ねてくる。
「……………。
言って理解してもらえるか判らないが、話そう。
あの聖杯は既に―――正純のものではない」
「………何?」
「私のような“守護者”がこの場に呼び出されることがその証明でもある。
聖杯戦争は霊格が高く、質のよい魂を集める儀式だろう?
なぜ掃除屋風情の矮小な魂がこの戦いに呼び出されるのだ」
「………守護者。ではおまえは“
「………そうだ。霊格の低い霊長寄りの英霊。それが私だ。
システム的にそんなものが呼び出される事自体、
既に歪みが生じ始めている証拠だ」
「……………」
“抑止の守護者”は魔術師にとって最大の障害。
自分が如何に恐ろしいものと対峙しているのか、時臣は改めて認識したらしい。
「第二に、聖杯自体が未だに成っていない事。
聖杯戦争も4回目だ。サーヴァントが朽ちていけば儀式が成就するという
このシステムにおいて、未だ聖杯の完成を見ていないのは何故だ」
「………それは」
「この前か、その前か。どこかで手違いがあった。
その為に聖杯は壊れ、本来の形で完成することが出来なくなった」
「随分と―――確証があるような口ぶりだな」
時臣はいぶかむ様にアーチャーを見る。
「………当然だ。
“冬木の聖杯”で起こりうる“悲劇”を―――私はよく知っている」
「なんだと?」
目を見開く時臣。
アーチャーが言った事の薄気味悪さに気付いたのだろう。
<冬木の聖杯で起こりうる悲劇をよく知っている>
それはありえないことだ。
なぜなら特定の時間軸に呼び出された英霊はあくまで、
“
消滅してしまうのが道理であるからだ。
故に、同じ英霊が同じ場所に召還されても以前の記憶を持って現れることは
ありえない。
だが―――アーチャーは言い切った。
“冬木の聖杯”で起こりうる“悲劇”を知っている、と。
「私が何者であるか―――それはどうでもいい。
ただこの儀式は成功しない。
致命的なバグを抱えながら儀式を続けても、リスクが高いばかりで
君達の求める根源への道は手に入らないだろう」
「……………」
「遠坂時臣、貴方は選ぶべきだ。
成功する可能性など無いこの儀式を続けるのか。
新たな可能性を求め、探求の道を踏み出すのか」
その言葉に黙り込んでしまう時臣。
返る言葉を待つアーチャーだが、よい返事が返ってくるとは思えなかった。
………実質分の悪い賭けだ。
アーチャーは魔術師が根源を目指すことの困難さをよく知っている。
何故なら、彼こそがその最大の障害、“抑止の守護者”であるからだ。
一から始めて根源へのアプローチを成功させるのに、
一体どれほどの年月がかかるのか。
一代では無理だろう。十代でも無理かもしれない。
百代かけても辿り着けないかもしれない。
魔術師達が往くのは、そんな不安定でリスクばかりが高い茨の道なのだ。
そして、ようやく入り口まで漕ぎ着けても、
彼らの前には抑止の守護者が立ちはだかる。
何百年という成果を粉々に破壊する。
塵一つとて残しはしない。
今時臣に強いているのは、
二百年の歳月をかけ子々孫々に受け継がれてきた大切な思いを破棄させる事。
親を愛し子を愛し、技術を磨き、極めて伝え、そうして繋げてきた
幾多の思いを、たどり着く道を。
―――諦めろと言っているに等しいのだ。
家政夫と一緒編第三部その20。
有史以来仇敵として存在し続けてきた魔術師と守護者。
互いは互いの理を持ってその道を諦めろと諭す。
だが、両者には両者なりの退けない理由があり―――。