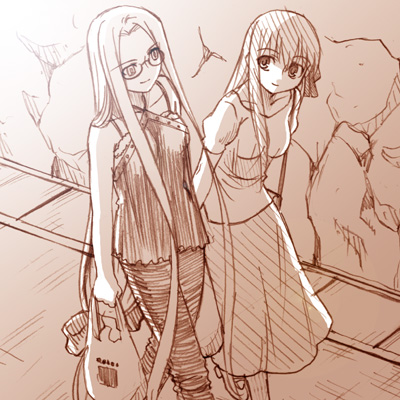
宵と暁の薄明かり
茜色の太陽が山の陰に隠れる頃。
「サクラ」
買い物袋を両手に、商店街の入り口で一人待つ主人に
ライダーは声をかけた。
「あ、ライダー」
買い物袋を抱えて嬉しそうに走りよってくる桜。
「ずいぶんな量ですね。持ちましょう」
「うん、ありがとう」
桜の持っていた買い物袋を受け取ると
両手に提げ歩き出す。
「結構重いですね。今日の夕食は何ですか?」
「士郎さん遅くなると言っていたから、今日はシチュー作ろうかと思って。
ジャガイモとか、人参とかお野菜もたくさん入ってるの」
「なるほど。
フフ、シチューですか。助かります」
少し安心したように微笑むライダー。
「……あれ?ライダー好き嫌いってあったっけ?」
「いえ、特には」
「………あ。お箸?」
「……………」
しまった、と言う顔であさっての方向を見るライダー。
「ふふ……。ライダーまだお箸慣れないの?」
「いえ、使えるのですが……。
やはりスプーンやフォークを使った食事のほうが楽です」
手振りを加えて説明するライダーを見て穏やかな表情になる桜。
「………どうしましたか?」
「え?………うふふ」
小首を傾げて微笑む桜。
「だってライダー、衛宮のおうちで初めて食事を食べた時
必要としません、みたいな事言ってたから。
お食事楽しみにしてくれるライダーが嬉しくて」
「………………」
そう言って本当に嬉しそうに笑う桜。
―――その笑顔は、とても優しくて。
遥か昔に失った、大切な人たちとの触れ合いを想起させた。
「………はい」
胸の内の痛みを隠し、ライダーは笑顔で返事をする。
聖杯を以ってしても、終わってしまった現実が覆る事は無い。
心に巣食う後悔を消す事など出来はしない。
だから、桜だけを見つめていればいい。
その夢は形を変えてココに在るのだから。
「あ」
何かに気がついたように桜が前方に目を向ける。
衛宮邸正門だ。話しているうちに到着したらしい。
「鍵開けてきますね」
バックから鍵を取り出して門へと駆けて行く桜。
夕日の残滓に照らされて、明るい足取りの主人を眩しそうに目で追う。
―――いまにも落ちそうだった夕日が。
山の陰に落ち、その光を隠したとき。
悪寒が走った。
「――――――――!」
ブオッ!
先を行く桜に一跳びで追いつくと、ライダーはその体を抱きかかえ
門の影へと飛んだ。
―――ザザッ!
着地し腕の中の桜を守るように抱きしめると、油断なく周囲に目を走らせる。
門の上、樹上、屋敷の前の長い道。
―――何も無い。攻撃された気配すらなかった。
「ラ、ライダー?どうしたの?」
目を白黒させながら腕の中の桜がライダーを見上げる。
突然の事に驚いているようだ。無理も無い。
「………いえ、気のせいでした。
驚かせて申し訳ありません、サクラ」
危険は無いと判断し、桜を開放する。
「あ………何か、感じたの?」
「…………はい。ですが………」
人の気配でも、攻撃の気配でもない。
それは悪寒。根拠の無い恐怖。
―――説明することは不可能だった。
「………うん、でも守ってくれたんでしょう?
ありがとう、ライダー」
考え込むライダーにぺこりと頭を下げる桜。
「………はい」
「もう、大丈夫?」
「はい、周囲には私たち以外の気配は感じません」
「良かった。それじゃ、おうちに入りましょ?」
握っていた鍵を見せて微笑む桜。
ガチャガチャと鍵を開けにかかる桜を尻目にライダーはもう一度だけ
周囲の気配を探る。
夕日が落ち、宵闇が空を覆う衛宮邸前は、平穏そのものだった。
『…………………』
なんとなく、心に残る不安を抱えながら
ライダーは桜と共に衛宮邸へと入った。
ライダーと一緒編-Sその3。
昼と夜の境界を人は”誰そ彼”と呼ぶ。
古人はその時間を魔が出ると信じていた。
それゆえに感じた悪寒なのか、それとも。